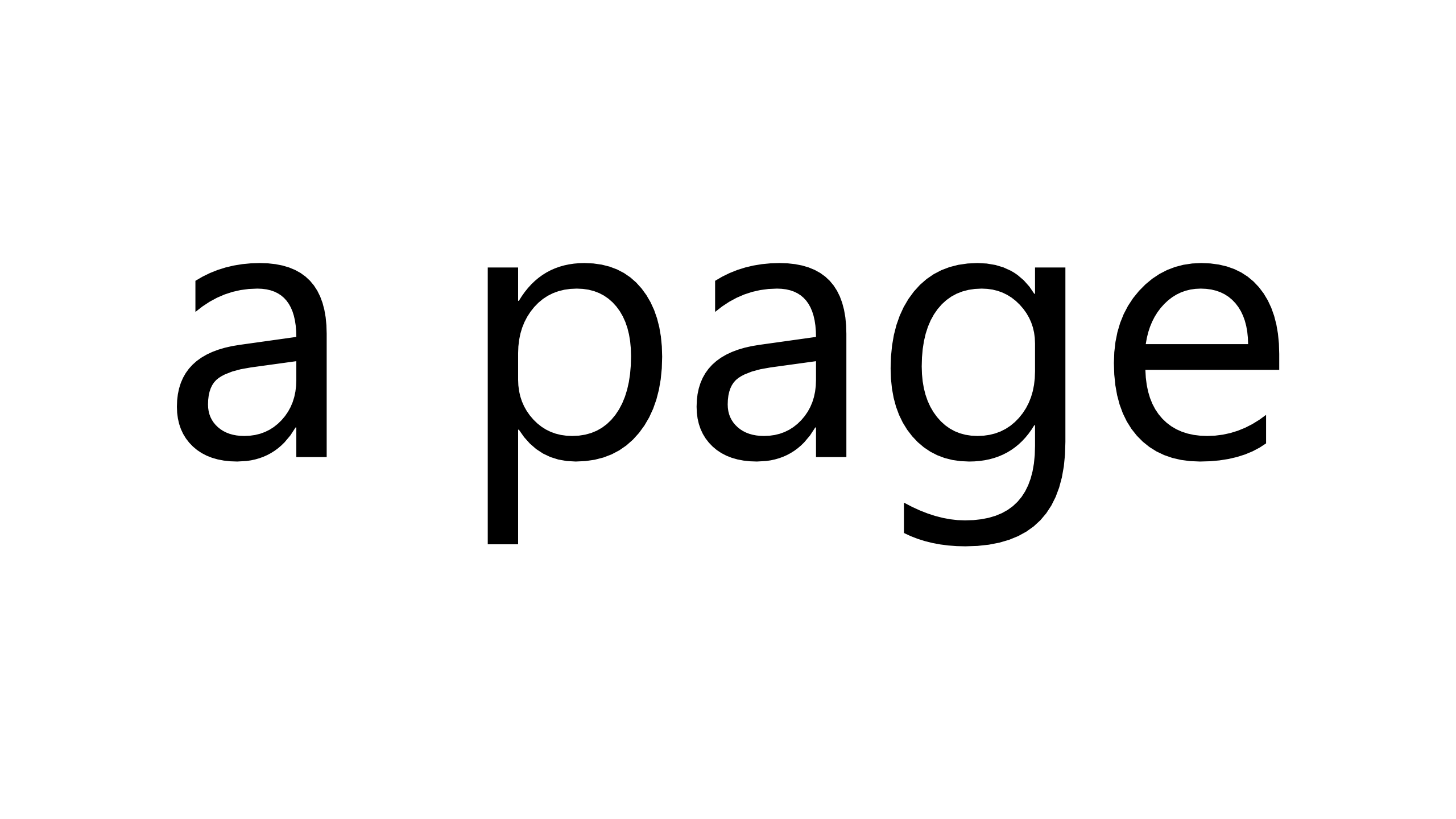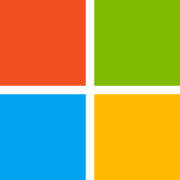音声コーデックOpusで録画した動画ファイルはブラウザで再生するのが一番手軽かもしれない

互換性を意識しながら設定
たまぁに画面録画をすることがあり、先日もコーデックは何にしようかと答えのない選択肢にうーんと頭を抱えていた。
いろいろな問題を解決しているおニューなコーデックを使いたいのだけれど、変なコーデックを使うと再生できないんだよねー。
とりあえず理屈ではこうやっておこうかなと一応考えが固まった。
- 動画コンテナとしてはHybrid MP4(つまり内部的にはFragmented MP4を使って、外から見れば普通のMP4として使えるので互換性もよき)
- 音声コーデックはOpus。ビットレートは160 Kbpsに設定するので劣化どうこうというよりかはファイルサイズの削減が狙い。
WindowsだとOpusだめっぽい?
ここで問題!動画コンテナはMP4なので当然Windows11標準のMedia Playerで開けるのだが、音声が再生されない。エラーポップアップも出てきて、再生無理といわれる。
たしかにWindowsのMedia Playerがサポートするコーデックのリストに、Opusの名はない。

これは困ったと思い、古き良きAACにコーデックを切り替えようと一時は思った。
いやいやOpusを使おうぜ!ブラウザで再生すればいいじゃん
が、しかし!
現代のWindowsユーザーが実際に動画を再生する環境は、この公式リストよりもはるかに多様で複雑。
友達に動画ファイルを渡したときに、友達はWindows Media Playerで開くだろうか。多くの場合、ブラウザで開いたり、既にインストールされている他のメディアプレイヤーを使用したりするはず。
現代的な観点から見ると、むしろブラウザでの対応状況の方が重要かもしれないってことです。

意外に知られていない事実ですが、ブラウザは現代において最も普遍的なメディアプレイヤーとして機能しています。WebベースのアプリケーションやサービスがOpusを標準採用している背景には、この状況があります。
パソコンでは動画ファイルをChromeやEdgeといったブラウザーにドラッグアンドドロップするだけで開けちゃいます。というか、視聴できちゃいます。
言われてみれば、YouTubeだってTwitchだって動画をストリーミングしているというだけで、動画を扱っているのはブラウザーです。画像や音声をブラウザーで開けるのと同様、当たり前すぎて気づきませんよね。
ということで、Chrome、Firefox、Edgeといった主要ブラウザは、すべてOpusを標準サポートしています。

つまり、友達はファイルをブラウザにドラッグ&ドロップするだけで、追加ソフトウェアなしに再生できるということです。
実際YouTubeも互換性のためにAACはあるものの、配信の標準としてOpusを使っています。
ということで、録画時は音声コーデックとして安心してOpusを使用し、ファイルサイズと効率性の恩恵を受けようかなと思います。他人との共有が必要になった場合には、あんまり気にずそのまま渡して、標準ソフトで開けなさそうならブラウザで開くことをおすすめしてみて、それでもだめなら、FFmpegでAACに変換しようかなあと思います。