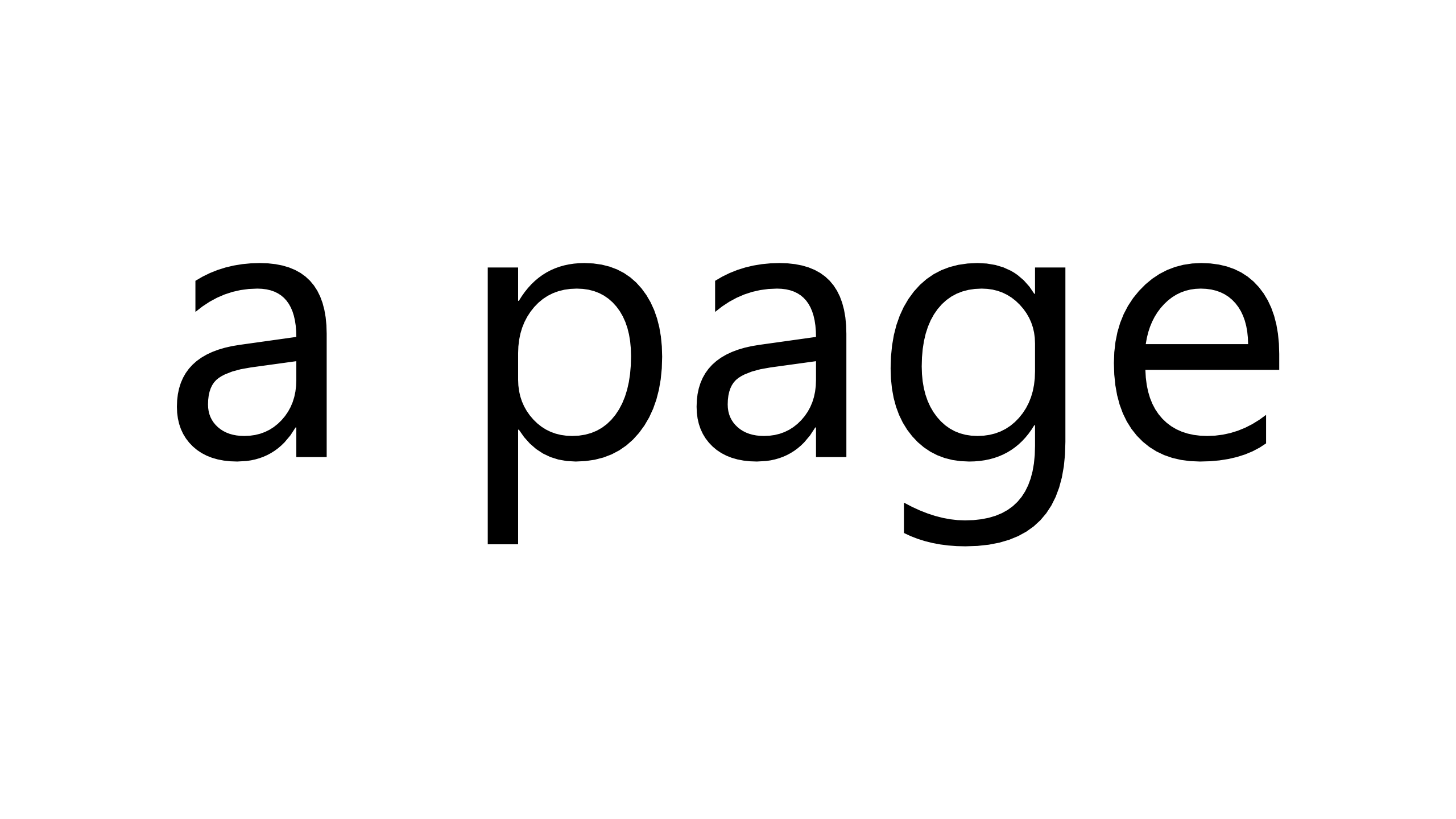ファイル階層を使ってメモは分類しない方がいいと思う

結論から
ObsidianやNotionを使ってメモを取るときはファイル階層(ディレクトリ階層?)を使って整理するのではなく、リンクを使ってメモを接続することで整理する方がいいと思う。
たとえば大学の講義ノート
フォルダーで管理をするとこんな感じでメモを管理することになると思う。
📂月曜3限専門英語
📝第1回講義メモ
📝第2回講義メモ
📝第3回講義メモ
📝第4回講義メモ
📝第5回講義メモ
📂月曜5限環境経済学
📝第1回講義メモ
📝第2回講義メモ
📝第3回講義メモ
📝第4回講義メモ
📝第5回講義メモ
見た目にはきれいに分類できていい気分になれるのがメリット。
問題はディレクトリは管理という意味以外をもたないこと。
知識というのはそれぞれが海上の孤島のように存在していて、それらをつなげていくことが大事なのかなって思っている。
リンクで管理するとこんな感じ。
📝2025年1学期
🔗📝専門英語
🔗📝第1回講義メモ
🔗📝第2回講義メモ
🔗📝第3回講義メモ
🔗📝第4回講義メモ
🔗📝第5回講義メモ
🔗📝環境経済学
🔗📝第1回講義メモ
🔗📝第2回講義メモ
🔗📝第3回講義メモ
🔗📝第4回講義メモ
🔗📝第5回講義メモ
ファイルの中にMarkdownのリンク(めもめも)[どこどこ]を埋め込むことでWebサイトのようにリンクをポチポチするだけでお目当ての場所にたどり着けるようになっている。
具体的にはこんな感じ。
## Markdownのメモメモ
これはいろんなメモをまとめるスーパーメモ
サブメモを列挙していく
- (サブメモその1)[./サブメモその1.md]
- (サブメモその2)[./サブメモその2.md]
- (サブメモその3)[./サブメモその3.md]
## サブメモその1
いろんなことをメモしていく。
めもめもめもめも。
📝2025年1学期のページをホームページのように扱うことで、階層構造をリンクとして表現したつもり。
ちなみにリンクを使ってメモを管理し始めるとファイルが一つの階層にたくさんできるので気になる人は気になる。
Obsidianでの使い方になるが、Obsidian Vaultのフォルダーにたまっていくことになる。
さすがに自分のメモと周辺の情報は異なるので、「自分が書いたメモ」と「他人の書いたメモ」と「添付ファイル」の三つに分けている。
添付ファイルはattachmentフォルダーにたまっていき、Webページの切り抜きはClippingフォルダーに保存するようにしている。
欠点は新規メモの作成はともかく、それをリンク形式で整理するのがめんどくさい。例えば第6回のメモを作ったとして、それをいちいちリンクとして書き込むのがめんどくさい。まあ、慣れです。
真意
Markdownがディレクトリ構造の変化に弱いことは結構言われること。
しかもわかりやすさのために、デフォではWikiリンクとなっているので普遍的なフォーマット化といわれると結構微妙。MarkdownなんだからMarkdownのお作法にそっていればいいのに。
また、Obsidianはデフォルトでノート間のリンクにWikilink形式の記述を採用しています。Wikilinkはフォルダ階層の変更に弱いだけでなく、ソフトウェアによって解釈がまちまちであるため堅牢性に欠けるので推奨できません。
https://jmatsuzaki.com/archives/28115
ディレクトリ構造の変化に弱いのだから、いっそ全部一つのディレクトリで管理してやろうと考えたわけ。ディレクトリはいじらない前提の使い方をすることで、うっかりリンクが壊れてしまうことをなくせるし、そもそもディレクトリをいじる用事がなくなる。
フォルダーを開いたときにずらっと表示されるので事実上の使い道もなくなるので、そもそもフォルダーを使う気すら起きなくなるはずだ。
必要なノートは検索機能を使ってノートのタイトルや全文検索機能でキーワードを頼りに検索していけばいい。最悪grepしてもいいし。
それにせっかくObsidianはネットワークとして表示してくれる面白機能があるのだから、それぞれのメモがどうつながっているのかネットワークとしてみてみるのは面白いじゃない。
Obsidianを使い始めたばかりの人の記事を見ていると、多くのメモが孤立しているネットワークグラフを見ることがある。
知識はつながってこそなのだから、せめて構造だけでもネットワークに落とし込んじゃえという感じ。
ファイルの場所を気にしなくて済むので、Ctrl + nでメモを一瞬で書き始められる。
めっちゃいいよ。