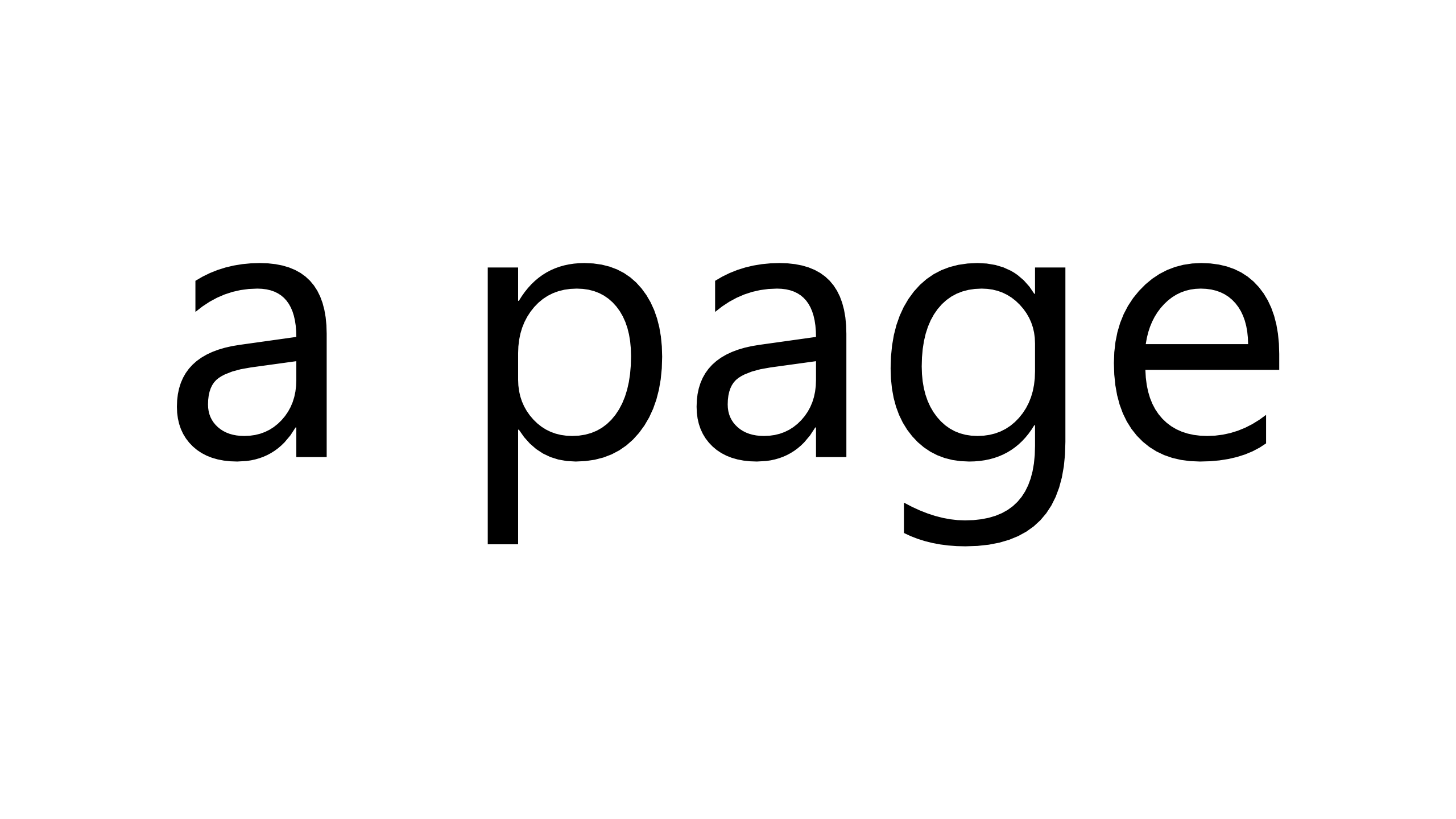白い壁に近づいても露出が変わらない物理学的理由
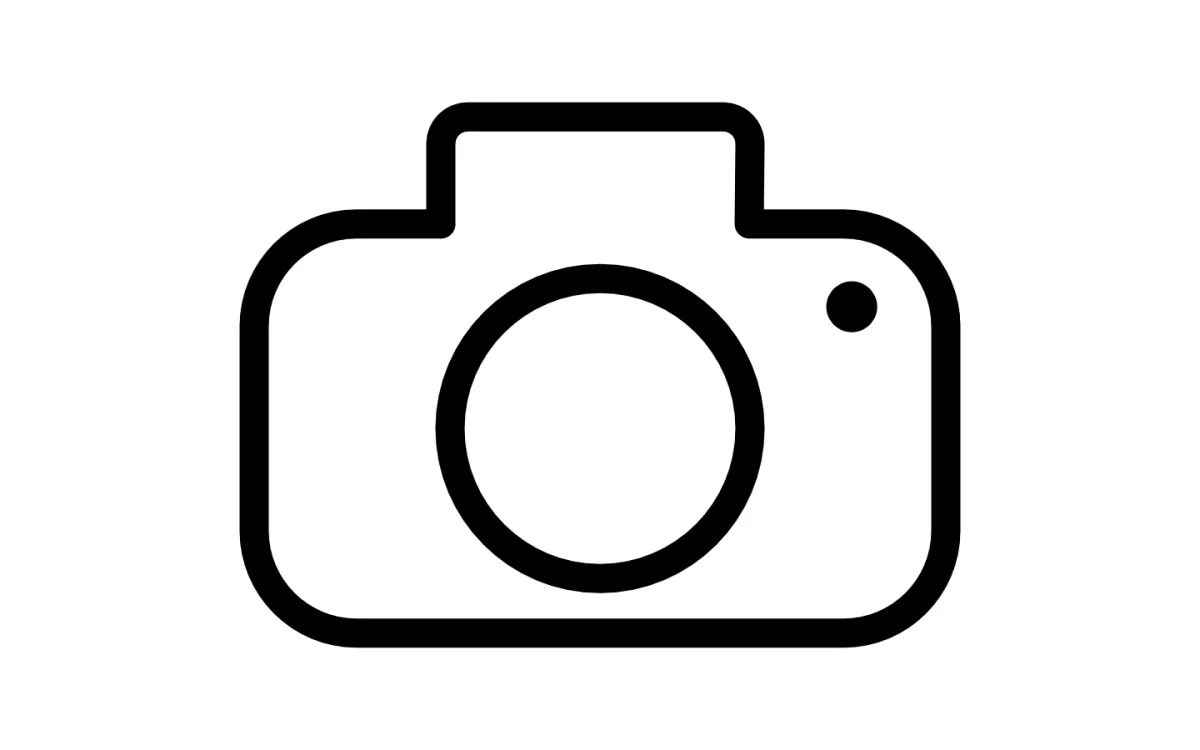
謎の現象
カメラを持っている方なら、ぜひ試していただきたい実験があります。カメラをマニュアルモードにして、均一に照らされた白い壁に向けてください。そして、壁から離れたり近づいたりしながら、露出計の針を観察してみてください。
驚くべきことに、露出計の針は全く動きません。
なんともオカシな現象です。なぜなら、電球やローソクにカメラを近づければ、露出計の針は確実に明るい方向に振れるからです。スピーカーに近づけば音が大きく聞こえるのと同じように、光源に近づけば明るくなるはずです。光も音も所詮エネルギーですから、近づけば大きくなり、離れれば小さくなる——これは物理学の基本です。
それなのに、なぜ白壁では変化がないのでしょうか?
この問題は、私が普段から見ているPhoto Cafeteriaさんのサイトに載っていたものです。サイトには「もしこれについて理論的に説明できる方がいらっしゃいましたら、是非お便りを頂ければと思います。もしご不明の方は、(残念ですが)引き続き幣サイトを覗いてみて頂ければ幸いです。」と書かれていて、ずっとわからずもやもやしていました。

ぜひPhoto Cafeteriaさんを訪問して問題について悩んでみてください

アレ?なんでだ?と思うハズ
「白壁は反射光で、電球は自ら光っているからだ」と思われるかもしれません。しかし、PCのモニターを全面白にしてカメラを近づけても、やはり露出は全く変化しません。PCのモニターは裏面に光源があり、自分で光っています。
さあ、何が起きているのでしょう?今回は、この謎について頑張って考えてみたので、物理学の基礎から徹底的に解明していきます。
簡潔な解説
「スピーカーに近づけば音が大きくなるのに、なぜ白壁に近づいても明るくならないのか?」
実は光も音も同じ逆二乗則に従っています。違うのは測定方法です。
音の場合
耳(マイク)がスピーカーに近づくと、その場所に届く音のエネルギーが増えるので大きく聞こえます。これは逆二乗則そのものです。
光の場合(入射光式露出計)
ストロボ撮影で使う入射光式露出計を白壁に近づければ、数値は確実に上がります。その場所に届く光のエネルギーが増えるからです。音と全く同じです。
カメラの内蔵露出計の場合(反射光式)
カメラの露出計は特殊で、「視野全体から集めた総光量」を測定しています。白壁に近づくと:
- 各点が明るく見える(立体角4倍→光量4倍)
- 視野が狭くなる(見える面積1/4)
この2つが相殺するため、センサーに届く総光量は変化しません。
点光源(電球)では相殺が起きない理由:電球は元々点なので、近づいても見える面積は変わらず、明るくなる効果だけが残ります。
結論
光も音も同じ物理法則に従います。白壁に近づけば、その場所の光の強さは確実に増えます。ただし、カメラの反射光式露出計は「視野全体の総光量」という特殊な測定をしているため、面光源では変化が見えないのです。
次元とは何か?
物理を理解する上で、「次元」という概念は非常に重要です。次元とは、物理量が持つ「種類」のようなものです。
たとえば、距離は「長さ」の次元を持ち、メートルで測ります。時間は「時間」の次元を持ち、秒で測ります。速度は「長さ÷時間」の次元を持ち、メートル毎秒で測ります。
なぜこれが重要かというと、物理的に意味のある式では、等号の両辺の次元が必ず一致するからです。これを「次元の整合性」と呼びます。
例えば、「距離 = 速度 × 時間」という式を考えてみましょう。
左辺の距離の次元は長さなので \([L]\) と表記します(ここで \(L\) は長さ(Length)の次元記号です)。右辺の速度×時間の次元は \([L/T] \times [T] = [L]\) となります(ここで \(T\) は時間(Time)の次元記号です)。両辺の次元が一致していますね。もし一致していなければ、その式は物理的に間違っているということです。
今回の議論では、次の次元記号を使います:
- \([L]\) は長さ(Length)の次元
- \([T]\) は時間(Time)の次元
- \([M]\) は質量(Mass)の次元
質量はエネルギーの次元を表すときに使います。
登場する物理量を整理する
白壁の謎を解くために、いくつかの物理量を定義していきましょう。
光のエネルギー
光源が放出する総エネルギーを考えます。運動エネルギー \(E = \frac{1}{2}mv^2\) を例に、エネルギーの次元を導いてみましょう。
質量 \(m\) の次元は \([M]\) です。速度 \(v\)(この \(v\) は速度を表す物理量の記号です)の次元は \([L/T] = [LT^{-1}]\) です。速度の2乗 \(v^2\) の次元は \([LT^{-1}]^2 = [L^2T^{-2}]\) となります。
したがって、エネルギー \(E = mv^2\)(定数は無視)の次元は次のようになります:
\[ \begin{aligned}[E] = [M] \times [L^2T^{-2}] = [ML^2T^{-2}] \end{aligned}\]
これは運動エネルギーだけでなく、位置エネルギーや熱エネルギー、光のエネルギーなど、すべてのエネルギーに共通する次元です。
照度:ある場所での光の強さ
光源からある距離だけ離れた場所での「光の強さ」を考えます。これを照度(Illuminance)と呼び、記号 \(I\) で表します(この \(I\) は照度を表す物理量の記号で、大文字のアイです)。照度は「単位面積あたりに届く光のパワー」なので、その次元は次のようになります:
\[ \begin{aligned} [I] = \frac{\text{エネルギー}}{\text{面積} \times \text{時間}} = \frac{[ML^2T^{-2}]}{[L^2][T]} = [MT^{-3}] \end{aligned}\]
実際の単位はルクス(lx)などですが、ここでは本質的な次元に注目します。
立体角:どれくらいの範囲を見ているか
ここで新しい概念を導入します。立体角(Solid angle)です。これは、ある点からどれくらいの「広がり」を見ているかを表す量です。
普通の角度(平面角)は弧の長さを半径で割ったもので、ラジアンという単位で測ります。\(\theta = s/r\) です(ここで \(s\) は弧の長さ、\(r\) は半径、\(\theta\) は平面角を表します)。
立体角は、これを3次元に拡張したものです。球面上のある領域の面積を、半径の2乗で割ったものです。立体角を \(\Omega\)(オメガ)で表すと:
\[ \Omega = \frac{A}{r^2} \]
ここで \(A\) はある球面上の領域の面積、\(r\) は球の半径です。
次元を確認すると次のようになります:
\[ \begin{aligned} [\Omega] = \frac{[L^2]}{[L^2]} = [1] \end{aligned}\]
立体角は無次元です。単位はステラジアン(sr)と呼ばれますが、これは本質的には「1」です。
球面全体の立体角は \(4\pi\) ステラジアンです。これは、球面全体の面積 \(4\pi r^2\) を半径の2乗 \(r^2\) で割ったものです。
輝度:面から見える明るさ
もう一つ重要な物理量があります。輝度(Luminance)です。記号 \(L_{\text{輝度}}\) で表します(照度の \(I\) とは異なる物理量であることに注意してください。また、この \(L\) は輝度を表す物理量の記号で、長さの次元記号 \([L]\) とは異なります)。
輝度は「ある方向から見たときの、単位面積・単位立体角あたりの光の強さ」です。これは少し複雑なので、丁寧に説明します。
ある光る面があるとします。この面の小さな領域 \(\Delta A\) から、ある方向の小さな立体角 \(\Delta \Omega\) に放出される光のパワー(単位時間あたりのエネルギー)を \(\Delta P\) とします(ここで \(\Delta\) は「微小な」という意味を表す記号です)。すると、輝度は次のように定義されます:
\[ \begin{aligned} L_{\text{輝度}} = \frac{\Delta P}{\Delta A \cdot \Delta \Omega} \end{aligned}\]
つまり、輝度は「単位面積あたり」かつ「単位立体角あたり」に放出される光のパワーということです。
次元を確認すると次のようになります:
\[ \begin{aligned} [L_{\text{輝度}}] = \frac{\text{パワー}}{\text{面積} \times \text{立体角}} = \frac{[ML^2T^{-2}/T]}{[L^2][1]} = \frac{[ML^2T^{-3}]}{[L^2]} = [MT^{-3}] \end{aligned}\]
照度 \(I\) と同じ次元ですが、物理的意味は全く異なります。照度は「ある面に当たる光」、輝度は「ある面から見える明るさ」です。
カメラのセンサーに届く光を計算する
さて、ここからが本題です。カメラのセンサーに光が届くメカニズムを、物理的に計算していきます。
レンズの役割
カメラのレンズは、被写体からの光を集めてセンサー上に像を作ります。レンズの有効口径を \(D\) とします(この \(D\) はレンズの直径を表す物理量の記号です)。レンズの開口面積は次のようになります:
\[ \begin{aligned} A_{\text{レンズ}} = \frac{\pi D^2}{4}\end{aligned}\]
これは円の面積の公式(半径 \(r\) の円の面積は \(\pi r^2\))から来ています。直径 \(D\) の場合、半径は \(D/2\) なので、面積は \(\pi (D/2)^2 = \pi D^2/4\) となります。
この開口面積が、被写体から光を集める「窓」の役割を果たします。
レンズが被写体を見る立体角
ここで重要な計算をします。被写体から距離 \(d\)(この \(d\) は被写体とレンズの間の距離を表す物理量の記号です)だけ離れた位置にレンズがあるとき、被写体から見て、レンズが張る立体角はどれくらいでしょうか?
立体角の定義 \(\Omega = A/r^2\) から、次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Omega_{\text{レンズ}} = \frac{A_{\text{レンズ}}}{d^2} = \frac{\pi D^2}{4d^2} \end{aligned}\]
ここで、被写体から見たときの「球面上の領域の面積」がレンズの開口面積 \(A_{\text{レンズ}}\) に相当し、「球の半径」が被写体とレンズの距離 \(d\) に相当します。
次元を確認しましょう:
\[ \begin{aligned} [\Omega_{\text{レンズ}}] = \frac{[L^2]}{[L^2]} = [1] \end{aligned}\]
正しく無次元です。
重要な事実:この立体角は距離の2乗に反比例します。つまり、距離が半分になると、立体角は4倍になります:
\[ \begin{aligned} d \to \frac{d}{2} \quad \Rightarrow \quad \Omega_{\text{レンズ}} = \frac{\pi D^2}{4(d/2)^2} = \frac{\pi D^2}{4d^2/4} = \frac{\pi D^2}{d^2} = 4 \times \frac{\pi D^2}{4d^2} = 4\Omega_{\text{レンズ}} \end{aligned}\]
これは、カメラを被写体に近づけると、被写体から見て「レンズがより大きく見える」ことを意味します。これは逆二乗の法則そのものです。
ケース1:白壁を撮影する場合
それでは、白壁を撮影する場合を詳しく見ていきましょう。
白壁の輝度
均一に照らされた白壁は、どこでも同じ照度 \(I_{\text{壁}}\)(この \(I_{\text{壁}}\) は壁が受ける照度を表す物理量です)で照らされています。白壁は拡散反射面(ランベルト面)なので、照度に比例する輝度を持ちます:
\[ \begin{aligned} L_{\text{壁}} = \frac{\rho \cdot I_{\text{壁}}}{\pi} \end{aligned}\]
ここで \(L_{\text{壁}}\) は白壁の輝度、\(\rho\)(ロー)は壁の反射率です(反射率は、当たった光のうち何割が反射されるかを表す無次元の量で、0から1の値をとります)。白壁なら \(\rho \approx 0.8\) 程度でしょう。分母の \(\pi\) は、拡散反射の幾何学から来る定数です。
重要なのは、この輝度 \(L_{\text{壁}}\) は一定ということです。壁を照らす照明が動かない限り、壁のどの部分も同じ輝度を持ちます。
レンズが見る壁の面積
距離 \(d\) から白壁を見たとき、カメラの視野角を \(\theta_{\text{視野}}\) とします(この \(\theta_{\text{視野}}\) は、カメラが一度に見える範囲の角度を表す物理量です)。このとき、見える壁の面積 \(A_{\text{視野}}\) は、おおよそ次のようになります:
\[ \begin{aligned} A_{\text{視野}} \approx (d \tan \theta_{\text{視野}})^2 \end{aligned}\]
ここで \(\tan \theta_{\text{視野}}\) は視野角の正接(タンジェント)です。視野角が固定されている場合、\(\tan \theta_{\text{視野}}\) は定数なので、見える面積は距離の2乗に比例します:
\[ \begin{aligned} A_{\text{視野}} \propto d^2 \end{aligned}\]
(ここで \(\propto\) は「比例する」という意味の記号です)
具体的には、距離が半分になると、見える面積は4分の1になります:
\[ \begin{aligned} d \to \frac{d}{2} \quad \Rightarrow \quad A_{\text{視野}} \to (d/2)^2 = \frac{d^2}{4} = \frac{A_{\text{視野}}}{4} \end{aligned}\]
レンズが受け取る光束
さて、レンズが白壁から受け取る光束(単位時間あたりのエネルギー)を計算しましょう。光束を \(\Phi\)(ファイ)で表します。
輝度の定義から、壁の面積 \(A_{\text{視野}}\) が立体角 \(\Omega_{\text{レンズ}}\) の方向に放出する光束は次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi = L_{\text{壁}} \times A_{\text{視野}} \times \Omega_{\text{レンズ}} \end{aligned}\]
これは、輝度が「単位面積・単位立体角あたりのパワー」だからです。面積 \(A_{\text{視野}}\) と立体角 \(\Omega_{\text{レンズ}}\) をかけることで、その方向に放出される総パワーが得られます。
具体的には次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi = L_{\text{壁}} \times A_{\text{視野}} \times \frac{\pi D^2}{4d^2} \end{aligned}\]
ここで、\(A_{\text{視野}} \propto d^2\) なので、比例定数を \(k\) として次のように書けます(この \(k\) は視野角に依存する定数です):
\[ \begin{aligned} A_{\text{視野}} = k d^2 \end{aligned}\]
これを上の式に代入すると次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi = L_{\text{壁}} \times k d^2 \times \frac{\pi D^2}{4d^2} = L_{\text{壁}} \times k \times \frac{\pi D^2}{4} \end{aligned}\]
\(d^2\) が約分されて消えました!
これが決定的です。
何が起きているのか?
数式だけでは実感が湧かないかもしれないので、具体的に考えてみましょう。
距離が \(d\) から \(d/2\) に半分になったとします。このとき、次の2つの変化が同時に起きます:
変化1:レンズが見る立体角が4倍になります(\(\Omega_{\text{レンズ}} \propto 1/d^2\))。これは、壁の各点から見て「レンズがより大きく見える」ことを意味します。したがって、壁の各点からレンズに届く光は4倍になります。
変化2:レンズの視野に入る壁の面積が4分の1になります(\(A_{\text{視野}} \propto d^2\))。近づくことで視野が狭くなり、壁のより小さな領域だけが見えるようになります。
この2つの効果が完全に相殺します:
\[ \begin{aligned} \frac{A_{\text{視野}}}{4} \times 4\Omega_{\text{レンズ}} = A_{\text{視野}} \times \Omega_{\text{レンズ}} \end{aligned}\]
見える範囲が狭くなることと、各点がより明るく見えることが、ちょうど打ち消し合うのです。
これが、白壁に近づいても露出が変わらない理由です。
ケース2:点光源(電球)を撮影する場合
では、電球の場合はどうでしょうか?ここで決定的な違いが現れます。
点光源の特徴
電球を点光源と近似します。つまり、サイズがほぼゼロで、全方向に光を放出する光源です。電球の総光束を \(P_{\text{電球}}\) とします(この \(P_{\text{電球}}\) は電球が全方向に放出する総パワーを表す物理量です)。
距離 \(d\) のレンズが電球から受け取る光束を計算しましょう。電球は全立体角 \(4\pi\) ステラジアンに光を放出しています(球面全体に放出しているということです)。レンズが張る立体角は \(\Omega_{\text{レンズ}} = \pi D^2/(4d^2)\) です。
したがって、レンズが受け取る光束は、電球の総光束のうち、レンズが張る立体角の割合だけです:
\[ \begin{aligned}\Phi = P_{\text{電球}} \times \frac{\Omega_{\text{レンズ}}}{4\pi} \end{aligned}\]
ここで \(\Omega_{\text{レンズ}}\) を代入すると:
\[ \begin{aligned} \Phi = P_{\text{電球}} \times \frac{\pi D^2/(4d^2)}{4\pi} = P_{\text{電球}} \times \frac{\pi D^2}{4d^2 \times 4\pi} = P_{\text{電球}} \times \frac{D^2}{16d^2} = \frac{P_{\text{電球}}D^2}{16d^2} \end{aligned}\]
分母に \(d^2\) が残っています!
これが白壁との決定的な違いです。
距離が \(d\) から \(d/2\) に半分になると、次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi' = \frac{P_{\text{電球}}D^2}{16(d/2)^2} = \frac{P_{\text{電球}}D^2}{16 \times d^2/4} = \frac{P_{\text{電球}}D^2}{4d^2} = 4 \times \frac{P_{\text{電球}}D^2}{16d^2} = 4\Phi \end{aligned}\]
光束が4倍になります。これは逆二乗の法則そのものです。
なぜ相殺が起きないのか?
白壁の場合は、「見える面積が1/4」と「立体角が4倍」が相殺しました。では、なぜ電球では相殺が起きないのでしょうか?
答えは、電球の見える面積が変わらないからです。
電球は点光源なので、サイズがほぼゼロです。距離を変えても、電球はセンサー上で1個の輝点、あるいは数ピクセル程度の像にしかなりません。つまり、\(A_{\text{視野}}\) は(ほぼ)ゼロのまま一定なのです。
白壁の場合、\(A_{\text{視野}} \propto d^2\) でしたが、電球の場合は \(A_{\text{視野}} \approx 0\)(定数)です。したがって、立体角の変化(\(\Omega \propto 1/d^2\))がそのまま光束の変化につながります。
これが、電球に近づくと露出が変わる理由です。
ケース3:PCモニターを撮影する場合
PCモニターは自ら光っているのに、なぜ白壁と同じように距離で露出が変わらないのでしょうか?
答えは、モニターは面光源だからです。
モニターの各ピクセルは確かに光っています。でも、モニター全体として見れば、一定の輝度 \(L_{\text{モニター}}\) を持つ「光る面」です(この \(L_{\text{モニター}}\) はモニター表面の輝度を表す物理量です)。この面の単位面積あたりの明るさは一定です。
したがって、白壁の場合とまったく同じ計算が適用されます:
\[ \begin{aligned} \Phi = L_{\text{モニター}} \times A_{\text{視野}} \times \Omega_{\text{レンズ}} \end{aligned}\]
ここで \(A_{\text{視野}} \propto d^2\) かつ \(\Omega_{\text{レンズ}} \propto 1/d^2\) なので、\(d^2\) が約分されて消えます。
モニターは「自分で光っている」ことは確かですが、「面として広がっている」ので、白壁と同じ振る舞いをするのです。
面光源と点光源の本質的な違い
ここまでの議論を整理しましょう。
光源に近づくと、確実にレンズが張る立体角は大きくなります(\(\Omega \propto 1/d^2\))。これは逆二乗の法則そのもので、必ず起きる現象です。
しかし、何を見ているかによって、結果が異なります。
面光源の場合
光源が面として広がっている場合、視野に入る面積 \(A_{\text{視野}}\) は距離の2乗に比例します(\(A_{\text{視野}} \propto d^2\))。
したがって、レンズが受け取る光束は次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi \propto L_{\text{輝度}} \times A_{\text{視野}} \times \Omega \propto L_{\text{輝度}} \times d^2 \times \frac{1}{d^2} = L_{\text{輝度}} \end{aligned}\]
面積の増加と立体角の増加が相殺され、光束は輝度 \(L_{\text{輝度}}\) のみに依存し、一定になります。
点光源の場合
光源が点に近い場合、視野に入る「光源の面積」は距離によらず一定です(\(A_{\text{視野}} \approx 0\)、定数)。
したがって、レンズが受け取る光束は次のようになります:
\[ \begin{aligned} \Phi \propto P_{\text{総光束}} \times \Omega \propto P_{\text{総光束}} \times \frac{1}{d^2} \end{aligned}\]
ここで \(P_{\text{総光束}}\) は光源の総パワーです。立体角の増加がそのまま光束の増加につながります。
境界線はどこか?
では、面光源と点光源の境界はどこにあるのでしょうか?
これは、光源のサイズ \(s\) が距離 \(d\) に比べて大きいか小さいかで決まります(ここで \(s\) は光源の実際の物理的なサイズ(長さ)を表します)。
もし \(s \ll d\)(光源のサイズが距離に比べて十分小さい)なら、点光源として振る舞います。電球に数メートル離れた位置から見る場合がこれに当たります。
もし \(s \geq d\)(光源のサイズが距離に匹敵するか、それより大きい)なら、面光源として振る舞います。白壁の前に立つ場合がこれに当たります。
具体例で実感する
理論だけでは実感が湧かないかもしれないので、具体的な数値で追ってみましょう。
白壁の場合
初期状態として、壁から2メートルの距離にいて、視野角60度で壁を見ているとします。このとき、見える壁の範囲は約2メートル四方です(\(\tan 30° \approx 0.58\) なので、見える片側の幅は約 \(2 \times 0.58 \approx 1.2\) メートル)。
壁から1メートルに近づくと、見える壁の範囲は約1メートル四方(面積は1/4)になります。しかし、レンズが張る立体角は4倍になります。
結果として、レンズが壁から受け取る総光束は変わりません。
電球の場合
初期状態として、電球から2メートルの距離にいるとします。電球のサイズは数センチです。
電球から1メートルに近づいても、電球の見える範囲はほぼ変わりません(依然として数センチ)。しかし、レンズが張る立体角は4倍になります。
結果として、レンズが電球から受け取る総光束は4倍になります。
まとめ
白壁に近づいても露出が変わらない理由は、次のメカニズムで説明できます。
光源に近づくと、レンズが張る立体角は確実に大きくなります。これは逆二乗の法則で、物理学の基本です。
しかし、面光源の場合、同時に視野が狭くなり、見える面積が小さくなります。この2つの効果が完全に相殺するため、レンズが受け取る総光束は変わりません。
点光源の場合、光源のサイズが変わらないため、相殺が起きず、立体角の増加がそのまま光束の増加につながります。
カメラの露出計は、センサーに届く光束を測定しています。面光源では距離に依存せず、点光源では逆二乗の法則に従う——これが、白壁と電球で異なる振る舞いを示す理由です。
めちゃくちゃシンプルに言うと:
白壁は「面」だから、近づくと見える範囲が狭くなる。この「見える範囲が狭くなる」と「各点が明るく見える」が完全に打ち消し合うから、トータルで変わらない。
電球は「点」だから、近づいても見える範囲は変わらない(元々点だから)。だから「各点が明るく見える」効果だけが残って、明るくなる。
逆二乗の法則は常に成り立っています。ただし、その効果が「どう現れるか」は、光源が点か面かで全く異なるのです。
これで、PCモニターが自分で光っているのに白壁と同じ振る舞いをする理由も明らかです。モニターは面光源だからです。
次回カメラを持ったら、ぜひ白壁と電球で実験してみてください。物理学の美しい対称性を、自分の目で確かめられるはずです。
補足:「スピーカーに近づけば音が大きく聞こえる」との違い
冒頭で「スピーカーに近づけば音が大きく聞こえるのと同じように、光源に近づけば明るくなるはず」という話をしました。でも、白壁では実際には変わらなかった。これは光が特別だからでしょうか?
実は違います。光も音も同じように逆二乗の法則に従っています。違うのはカメラの露出計が特殊な測定方法をしているということなのです。
露出計には2種類ある
ストロボ撮影をしたことがある方なら、露出計に2つのタイプがあることをご存知かもしれません。この2つの測定方法の違いが、今回の現象を理解する鍵です。
入射式露出計

こういう露出計です
ストロボ撮影で使う単体露出計(入射光式露出計)は、被写体の位置に露出計を置いて、白い半球(インシデントドーム)を光源に向けます。これは「被写体の場所に実際に届いている光の強さ」を直接測定しています。これを白壁の前に置いて、壁に近づけていったらどうなるでしょうか。答えは明白です。数値は確実に上がります。壁から反射される光のエネルギーが、逆二乗の法則に従って強くなるからです。
これは、人間の耳がスピーカーに近づくと音が大きく聞こえるのと全く同じ現象です。その場所に届くエネルギーが大きくなるのです。光も音も、ここでは同じように振る舞っています。
反射式露出計
一方、カメラの内蔵露出計(反射光式・TTL露出計)は、全く違う測定をしています。レンズを通って入ってきた光をセンサー面で測定します。つまり、被写体から反射されてカメラに戻ってくる光を測っています。そして重要なのは、視野全体から集めた光の総量を測定しているということです。
反射光式露出計は、被写体から反射した光を測定する方式で、カメラに内蔵されている露出計と同じです。
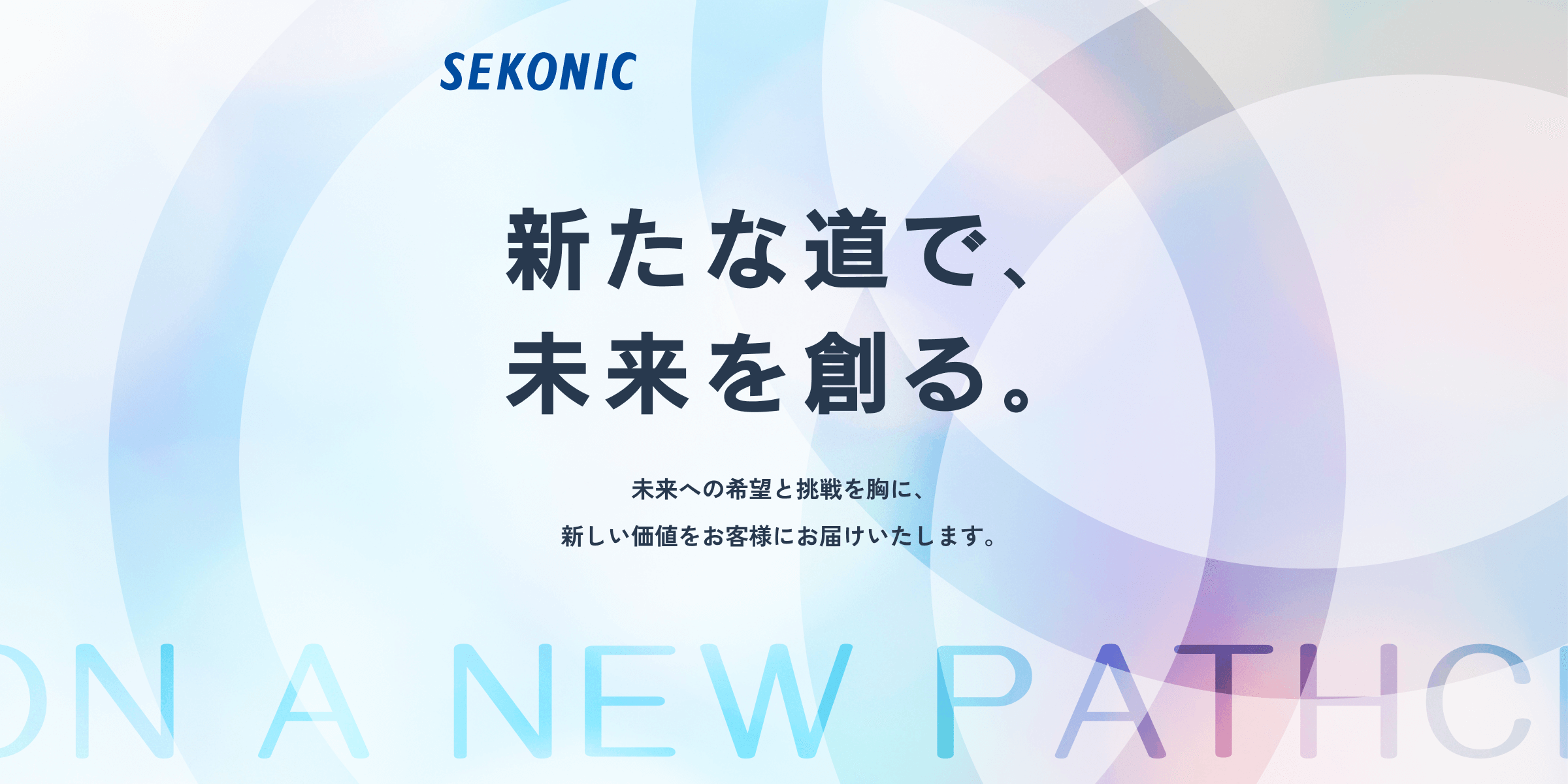
これが、白壁に近づいても変わらない理由です。視野内の各点からの光は確かに強くなりますが、同時に視野が狭くなって見える範囲が小さくなります。この2つの効果が完全に相殺するため、センサー全体に届く総光量は変わらないのです。
つまり、同じ「露出計」という名前でも、入射光式と反射光式は全く異なる物理量を測定しているのです。入射光式は「ある場所での光の強さ(照度)」を測り、反射光式は「視野全体から集めた光の総量」を測っています。
実際の撮影での違い
ストロボ撮影の経験がある方なら、実際に体験したことがあるかもしれません。ストロボの光量が足りないとき、ストロボを被写体に近づければ、入射光式露出計の数値は確実に上がります。これは逆二乗の法則そのものです。
でも、もしカメラの内蔵露出計で白壁を測定しながら近づいても、数値は変わりません。同じ「露出計」なのに、測定結果が全く違うのです。
ちなみに、プロのカメラマンがストロボ撮影で入射光式露出計を使うのには理由があります。入射光式は被写体に実際に当たっている光の量を直接測るので、被写体の色や反射率に影響されません。白い服を着ていようが黒い服を着ていようが、同じ光量なら同じ値を示します。
一方、カメラの反射光式露出計は、被写体が白いと「明るすぎる」と判断して露出を下げようとしてしまいます。これは白飛び防止の自動補正が働くためです。雪景色を撮ると暗く写ってしまう、という経験がある方もいるかもしれません。これは反射光式露出計が「白い被写体から反射されてくる光が多い」ことを「明るすぎる」と誤解してしまうからです。